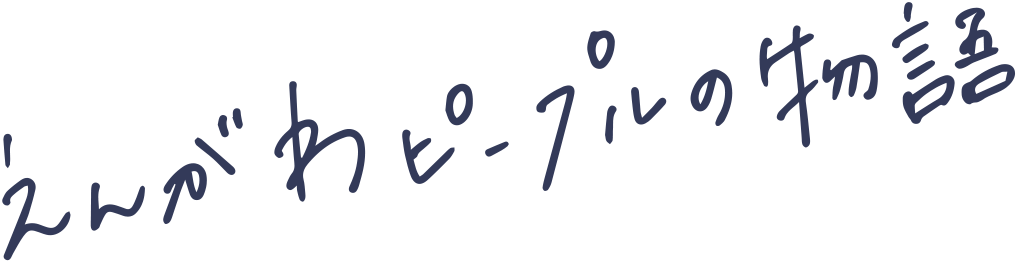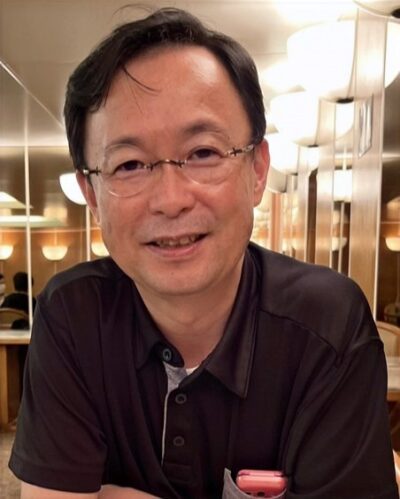2025.07.24
地域を編み、未来を描く~ソーシャル・キャピタルの物語〜interview vol.2
地域や社会の中で、信頼しあい、おたがいさまと思い合える、豊かなつながりを育む大切さ。これを「ソーシャル・キャピタル」といい、ポスト・コロナの社会を支える価値概念としてとても注目されています。
いぶき福祉会(以下、いぶき)では、日々の営みをこのソーシャル・キャピタルを豊かにする活動として物語り、寛容で協働する社会を創っていきたいと考えています。
いぶきでは、2023年度の年次報告書でソーシャル・キャピタルについてのアンケートを実施しました。
多くの方が、いぶきとつながることでの新たな気づきや暮らしの変化があることを伺い知り、そのエピソードをお伝えすることで、また新たな学びと対話につなげられると感じました。そんな思いで始めたインタビューをお届けします。
共感や発見が満載だと思います。お楽しみいただければ幸いです。
第1回は、千葉県四街道市の地域づくりセンターでNPOなどを応援する活動を続けておられる勝又恵里子さんにお話を伺いました。
第2回も引き続き、勝又さんとのお話しです。
(お話しを伺った人:いぶき福祉会北川、山本/めぐる 木村、長谷川)
- 執筆:
-
いぶき福祉会
いぶきの商品がもつ物語をきっかけに
勝又:よい意味でのゆるさがある一方で、実はしっかり計画的に少しずつ前進しているのが、いつもすごいなと思っています。
北川:すごくしたたかな人みたいですね(苦笑)。ということは勝又さんと出会ってからの12年間、ぼくたちは小さな歩みを続けてこられたということなんですね、きっと。
木村:「ゆるい」というのは、北川さんからもよく聴く言葉です。それって何だろうなと考えました。勝又さんもNPOクラブの活動で、さまざまな団体をご存じですよね。千葉にも多くの団体がある中で、何がそれほど魅力的なのか、もう少し聴きたいと思いました。
勝又:言葉で伝えるのが難しいですね。先日、いぶきのパックのお茶を買って人に贈ったら、すごく喜んでくれました。そんな時、ここぞとばかりにいぶきの話をするんです。
木村:いぶきの商品には多くの物語が込められていて、それがきっかけとなり、伝えたいことが自然と湧き出てくるんですね。
勝又:そのおかげで、周囲の人にも伝えることができるんです。マドレーヌや百々染(ももぞめ)などもそうですね。
ソーシャル・キャピタルの関係性を育むには
木村:いぶきがソーシャル・キャピタルの関係性を育もうとする中で、つながる相手が固定化するという課題があると感じています。特に遠方の方や若い世代への広がりがまだ十分ではありません。そこで、勝又さん2号、3号を生んでいくにはどうしたらよいのか、ヒントをいただきたいんです。
勝又:ヒントになるかわかりませんが…。以前、北川さんの講座を私たちが主催し、その際に韓国のジョさんと「いぶきに行きたいね」と盛り上がり、昨年一緒に訪れる機会がありました。
木村:つまり、北川さんが各地で話をすることが重要だということですね。
北川:勝又さんに言われたら、ぼくはどこへでも何度でも行きます。勝又さんがいぶきのことを自慢してくれるのは、いぶきのためではなく、自分ごととして語ってくれているように感じています。それがすごくうれしくて、もっと情報をお届けしたくなりますね。そういう人を増やしていくことが楽しいと感じています。

左からいぶき山本、勝又さん、ジョさん
いぶきのファンになってもらうには
勝又:木村さんの話にもありましたが、いぶきのファンを増やしたいと思っていますか?
北川:はい。遠くの方でもいぶきを知っている人はたくさんいます。施設同士のつながりやクラウドファンディング、過去の募金活動を通してかかわった方もいます。しかし、その方々にファンになってもらう道筋は、まだ十分につくれていません。「もっとこうすればファンが増える」「こうすれば自分がもっと楽しくなる」と思うことはありますか?
勝又:難しいですね。
山本:オンラインのお話会や会員向けイベントなどを開催しても、すごくたくさんの方が参加するわけではありません。しかし、参加者とはすごくなかよくなれる実感があります。勝又さんは積極的に参加してくださっていますが、ご自身の活動に何か学びがあるからでしょうか?
勝又:オンラインの案内があると、まず参加しようと思います。この前の「かりんとう誕生秘話」のトークイベントも、みなさんが失敗談も含めて楽しそうに話されていて、信頼関係が伝わってきておもしろかったです。
すぐにわからない言葉に、惹かれる人と、あきらめる人
勝又:いぶきでは時々、聞き慣れないキーワードが出ますよね。すぐにはわからなくて、「何だろう?」と思うことがあります。
北川:それはよい意味で、ということでしょうか?
勝又:言葉の意味がわからないからこそ、知りたいと思うんです。「ケアリング・カフェ」という言葉が出た時も自分で調べました。
北川:横文字ばかりでわかりにくいと言われることもあります。でも、他に適切な表現がないからこそ使っています。一歩踏み込んで知ろうとする人もいれば、そこで引いてしまう人もいます。
勝又:「ケアを文化に」というビジョンも、何度も聴くうちに「こういうことなのかな」と理解が深まってきました。
北川:「ケアを文化に」という言葉を説明できる人が、いぶきの中でもまだまだです。勝又さんがその言葉を口にしてくれることが、とてもうれしいですね。
木村:今の話、おもしろいですよね。わかりやすい言葉が必ずしもよいわけではなく、難しい言葉だからこそ引っかかり、興味を持つ人もいれば、逆にシャットダウンしてしまう人もいる。そのバランスの難しさを感じました。
北川:勝又さんがそこで惹きつけられるのは、やっぱりいぶきに圧倒的な信頼感を持ってくださっているからだと思います。信頼してくださる方がいぶきのことをご自身の言葉で語っていただけるように、まだまだできることがあるのではないかと感じました。熱心な支援者の方を大切にしていくことも、ソーシャル・キャピタルを育む上でも大切ですね。
輪が広がっていく喜び
北川:今回のインタビューを記事にし、多くの方に読んでいただきたいと考えています。「こういうかかわり方もあるのか」と気づいたり、「こんなことをしてみたい」と思ったりするきっかけになればうれしいですね。よいことばかりでなく、叱咤激励も含めてご意見をいただくことで、ぼくたちのエネルギーにもなります。
勝又:こういう話になるとは思っていませんでした。でも改めて、いぶきとは自分にとって何なのかを考えました。
北川:また見えてきたことがあれば、共有してくださいね。
勝又:そういえば、「ほとり」のお店のガラスにクラウドファンディング支援者の名前が書かれていますよね。そこに千葉の知人の名前を見つけて、すごくうれしかったんです。何回かお会いしたり、Facebookの中でお会いしている人も見つけて、うれしいですね。
北川:その話を聴くだけで、うれしいです。ほとりでお待ちしていますね。
長谷川:勝又さんの、千葉のお知り合いの方がほとりに寄付されてうれしかったというお話を聴いて、千葉県のいぶきファンクラブのような、ゆるいつながりができると、勝又さん自身もよりうれしくなったりとか楽しくなったりするのかなと思ったりしました。
北川:なるほど。以前から、tabita便の商品を語る会とか、いぶきのおいしいものを一緒に食べながらおしゃべりする会もよいねという話があったので、ちょっと真面目な話もよいですし、そうやって楽しくやるのもよいですし、何かやりたくなっちゃいました。
勝又:私だけがいぶきのことをよいと言っているというのではなくて、他にもいぶきのことを知っている方や一緒にいぶきに行った方もいるので、そういうふうに少しずつ輪が広がるとよいですね。
北川:勝又さん、今日は本当にありがとうございました。
まとめ
いぶきが持つ物語は、人と人とのつながりを生み出し、広げていく力を持っています。
勝又さんのように、その魅力をご自身の言葉で語ってくださる方の存在で、いぶきの輪はより大きく、深くなっていくのだと思います。
言葉に心を留めて、理解しようとしてくださり、そして共感して伝えるてくださること。
その一つひとつが、いぶきのビジョン「ケアを文化に」をともにはぐくむことになります。
今回の対話を通して、その可能性を改めて感じています。
今後も、いぶきに関わる方へのインタビューを通して、ソーシャル・キャピタルを育むための具体的な取り組みや、未来への展望を深めてきます。